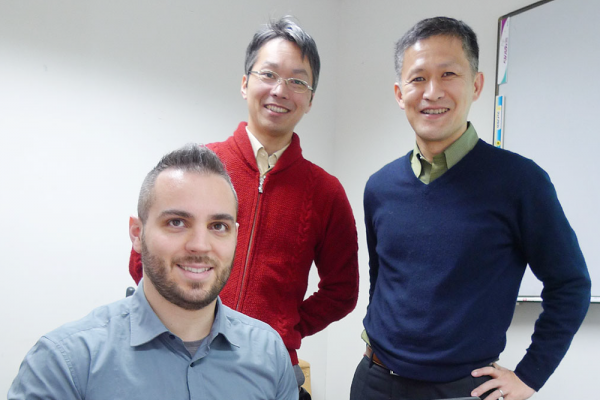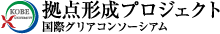これまで新学術領域「グリアアセンブリによる脳機能発現の制御と病態」で培った日独間での交流により、既に開始されている若手共同研究に加えて、日本側の拠点機関及び協力機関において、その強みを活かして行われている国際共同研究を足がかりに、国際合同セミナー、国際グリアコンソーシアムによる技術・リソース共有、新規開発等を介して、共同研究を強力に推進するために各研究機関に客員ポストの配備を行い、特に若手を中心とした国際共同研究を積極的に支援します。
共同研究例
- 神戸大(和氣)-カナダ(Prof. Robitaille)
- 山梨大(小泉)-ドイツ(Prof. Kirchhoff)
- 理研(平瀬)—デンマーク(Prof. Nedergaard)
- 神戸大(和氣・古屋敷)—マウントサイナイ大学(Prof. Russo, Prof. Morishita)
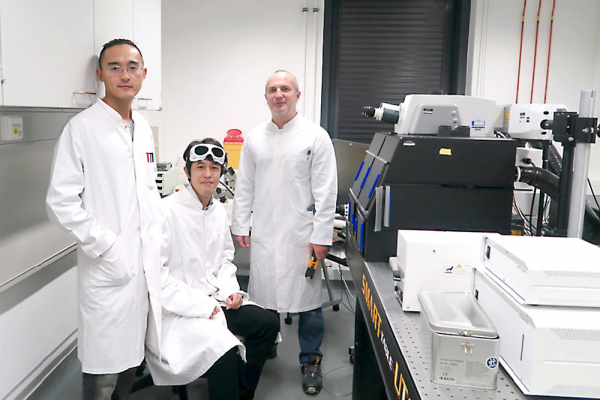
セミナー
各国持ち回りで年 1 回の国際グリア合同セミナー(国際セミナー)及び若手セミナーを行います。国際セミナーは共同研究の進捗状況の確認を主な目的とし、技術・リソースの共有、技術開発のための情報交換を通じた国際共同研究の推進も積極的に行います。
さらに、本事業終了後も本国際セミナーを定例化するシステムを確立します。若手セミナーでは、若手による国際共同研究の提案、マッチング及びその評価を行うとともに、若手研究者育成のための技術セミナーを開催します。

研究者交流
共同研究やセミナーの実施を通して研究者交流を行い、国際グリアコンソーシアムを形成することで研究者交流を推進します。さらに、本計画では、若手研究者の交流・共同研究を強力に支援することを大きな柱としています。
グリア研究は新しい学問であり、20 年、30 年後の「グリア脳科学」を世界で牽引していく人材を発掘・育成することが、日本のグリア脳科学、ひいては日本の脳科学全体の発展に重要です。
そのために、世界最先端のグリア研究を先導している各研究機関の研究室間での国際共同研究・交流を推進させるとともに、既に日独間で交流が始まっている二国間グリア若手の会を拡大し、「国際グリア若手の会」を構築し、その企画・運営にも若手研究者の参画を促します。
具体的には、若手セミナーの企画・開催、若手共同研究の提案と実施などを行い、若手研究者による研究室の行き来を加速し、国際的人材の育成につなげていきます。